特集 バラエティーなう
テレビ・バラエティーはどこへ行く?月刊民法2010年5月号
さて、BPOの放送倫理検証委員会が出した「最近のテレビ・バラエティー番組に関する意見」を受けて、バラエティー番組が抱える問題点、これからの可能性とそのあり方を考えていこうというのが本稿の狙いである。
独自の発展を遂げたジャンル
以前から僕は、日本ほどバラエティー番組が好まれている国はほかにないのではないかと考えていた。
「いや、そんなことはない。現に、これだけ多くのバラエティーヘの抗議が寄せられているではないか」とおっしやる方もいるだろう。それは確かにそうなのだが、では、テレビ番組の中でバラエティーの占める割合が日本よりも高い国がほかにあるだろうか。
テレビに登場するお笑い芸人の数がこれだけ多い国も珍しいだろう。「リアクション芸人」や「ひな壇芸人」の存在も日本独白のものなのだ。
僕が教えている江戸川大学の中国人留学生は、来日して間もないころに日本のテレビを見て、あまりのバラエティーの多さと、それまで持っていた「日本人は真面目」というイメージとのギャップに、まず驚いたという。
意見書のバラエティーって何だ?」という項では、「広辞苑」(第6版)から「落語・漫才・曲芸・歌舞など諸種の演芸をとりまぜた演芸会。また、その種の放送番組」という項目が紹介され、「いまどきこの例にあるような演芸だけで成り立っているバラエティー番組など、かえって珍しい」バラエティーは出演者によっても、構成や演出の仕方によっても定義される番組スタイルということである」と書かれている。
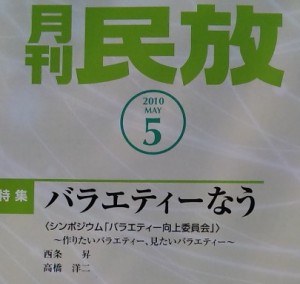
もともと、バラエティーという芸能ジャンルはステ~ンーショーの一種としてアメリカで成立したもので、フレヨドーアステアとジュディー・ガーランドが主演した映画『イースター・パレード』(48年)で往年のバラエティーのステージの雰囲気を味わうことができる。現在も、ラスベガスではvarietyの頭文字からとった「V」という題名で、曲芸とマジョクとお笑い芸などを並べて見せる形式のステージーショーが上演されている。日本でも、昭和初期の浅草や日比谷の劇場では[ヴァラエテー]といった表記でレヴューやコメディーとともに盛んに上演されていた。 日本にテレビが誕生してからは、アメリカの『ペリー・コモーショー』などの影響を受けて制作された『光子の窓』『シャボン王ホリデー』『九ちゃん!』(以上、日本テレビ)、『夢であいましょう』(NHK)といった番組は一般的に「バラエティー・ショー」と言われることが多かった。
最近のバラエティー番組はバラエティー・ショーという表現がニュアンス的にしっくりこないものが大半である。つまり、日本のバラエティー番組は、バラエティー・ショーという表現から「ショー」が取れ、単にバラエティーと言われるようになった瞬間から独白の発達を遂げたと言えるのではないか。
良くも悪くも、現在の日本のバラエティーは、われわれ日本人の持つ気質や好みを反映して成立したものであることは間違いないと思われるのだ。
「テレビ芸」がお笑いを変えた
そんなことを考えていたら、BPOの意見書を受けた二つの番組がこの春に相次いで放送された。『めちゃ2イケてるッ!』の「プロフェッショナル めちゃイケの流儀 超緊急スペシャル」(2月27日放送)と『悪いのはみんな萩本欽一である』(3月27日放送)。どちらも制作はフジテレビである。
意見書では、バラエティーに対する苦情や抗議を、①下ネタ、②イジメや差別、③内輪話や仲間内のバカ騒ぎ、④制作の手の内がバレバレのもの、⑤生きることの基本を粗末に扱うこと、という5つに分類しているが、このうち②と③の具体例として『めちゃイケ』に対するものが(番組名こそ書かれていないものの)挙げられていた。
これらに対する一種の回答として作られたのが、前者の「超緊急スペシャル」だった。意見書にある具体例を紹介しつつ、どうしたらもっと安全に面白くできるかをナインティナインの岡村隆史が番組スタッフと相談しながらテストを繰り返していく。手錠をかけて動けなくなったバナナマンの日村勇紀を熱湯に突き落とした企画への抗議を受けて、岡村が両足をタオルで結んだり、寝袋に全身を入れた状態のままで熱湯に突き落とされたり。バレンタインデーにちなんで溶かしたチョコを加藤浩次と鈴本紗理奈の頭からかけて「チョコフォンデュ」にした企画への抗議に対して、岡村がミキサー車から流されるドロドロの生コンクリートを大量に浴びて「生コンクリートフォンデュ」状態になったり。
意見書の「私たちは、バラエティーが萎縮することを望まない」という一文を受け止めた岡村が、ことあるごとにスタッフに「萎縮すんなよ」と言いながら、自ら何度もヒドイ目に遭う様子が笑えた。一方で、「張り扇で叩かれるのを、イジメを助長してるみたいに言われるけど、そうじゃないワケ。ただ、学校でイジメられている子が、俺らが頭叩かれるのを見て笑ってくれたら、それでいいワケ」と熱く語る岡村の表情も、ひときわ印象に残った。
寝袋に入ったまま熱湯に突き落とされたり、頭からコンクリート液を浴びたりといった笑いは、スラップスティックコメディー(=ドタバタ喜劇)の笑いに通じるものがある。そのルーツはチャップリンやキートンやローレル&ハーディーらの無声喜劇映画にまでさかのぼることができる。彼らは皆、誰よりもヒドイ目に遭うことで笑いを誘っていた。警官隊に扮した数人のコメディアンが走る車の後部にとり付けられたロープにつかまり、うつ伏せのまま地面を引きずられ、しまいに電柱に全員がグルグルと巻き付いてしまう短編喜劇映画の場面などは、まるで漫画を見ているような面白さがあったものだ。
ザードリフターズの『8時だヨー全員集合』(TBS) のコントもスラップスティックな笑いを狙ったものだったが、加藤茶の「チョットだけよ」やウンコの作り物などのネタ、食べ物を投げ合うギャグなどに多くの苦情が寄せられた話はよく聞くものの、志村けんが大量の水をかぶったり、粉まみれになったり、いかりや長介にメガホンで叩かれたりするギャグに対して「イジメを助長する」との抗議があったという話はあまり聞かない。
人によってイジメを連想させる「リアクション芸」や「被虐芸」がいつから始まったかと言えば、『金曜10時!うわさのチャンネル!!』(日本テレビ) のせんだみつおからではなかったか。プロレスラーのザ・デストロイヤーに4の字固めをかけられたせんだが涙を流して本気で痛がっているように見せ、共演の和田アキ子らがその様子を見て大笑いするという構図も生まれた。その後、コントやコメディーという枠を外して、バラエティーの企画としてタレント本人のギャラのままでもヒドイ目に遭ったり遭わせたりすることが主流となり、イジメに関する視聴者の苦情が増えたように思う。
一方の『悪いのはみんな萩本欽一である』は、『空気人形』『誰も知らない』などで知られる是技裕和監督が演出を担当。バラエティーに「イジメ」や「素人いじり」などの要素を持ち込んだ元凶を萩本としたうえで、被告人・萩本をめぐる法廷劇という設定でバラエティーとは何かを探っていく異色作であった。 『24時間テレビ』(日本テレビ)のメインパーソナリティーを務めたころの萩本には、世間的に「いい人」とのレッテルが貼られていたから、「イジメ」の笑いとすぐに結びつかない人も多いだろう。しかし、無茶な注文をアドリブでしつこく連発することで相棒の坂上一郎を困らせ、時には飛び蹴りをくらわせるコント55号時代の若き日の萩本の姿を知る人なら納得するに違いない。坂上が本当に困ったり疲れたりしているように見せるのが抜群に上手かった分、余計に当時の萩本の芸風からはサディスティックな匂いが漂っていた。
後に、若手芸人に無茶な注文を出して過酷な旅をさせる企画などで一世を風扉した『電波少年』シリーズ(日本テレビ)のプロデューサーを務めた日本テレビの土屋敏男氏は、かつて萩本の番組のディレクターを担当したころにそのサディスティックな笑いの作り方から大きな影響を受けたという。
下ネタに関しても、萩本は女性タレントを野球拳で脱がせていく『コント55号の裏番組をぶっとばせ!』(日本テレビ)という大きな足跡を残している。 また、素人いじりを多用した一連の。欽ちゃん番組”で萩本は独白の「テレビ芸」を確立した。ここでいう「テレビ芸」とは、本来はプロの作り手や演じ手による「表現としての笑い」を、視聴者の生活に身近な「日常としての笑い」の体裁で仕立て直し、極めてノンフィクション的に見せていく手法のことである。思えば、バラエティー・ショーから「ショー」という言葉が取れて、単にバラエティーと呼ばれるのにふさわしい番組が増えるのも、そのころからであった。
そういった意味で、『悪いのはみんな萩本欽一である』という番組タイトルに倣って「悪いのはみんなフジテレビである」と言うことも可能だろう。『欽ちゃんのドンとやってみよう!』で萩本の「テレビ芸」確立の場を与えたのも、『笑ってる場合ですよ!』や『笑っていいともとで「日常としての笑い」を大胆に取り入れたのも、『オレたちひょうきん族』でのディレクターの出演や芸人同士の暴露合戦といった楽屋オチの連発で意見書にある「内輪話や仲間内のバカ騒ぎ」の笑いを作るキッカケも、すべてフジテレビなのだ。さらに言うならば、「楽しくなければテレビじゃない」をキャッチフレーズに、情報番組、音楽、スポーツ、ドラマに至るまでバラエティー化を推し進めたのも、同社であった。
今回、BPOの意見書に素早く対応して作られた二つの番組がともにフジテレビ制作だったこと、そして、ともに優れた意欲作であったことに、同局のバラエティー作りにおけるプライドと意地を感じることができた。
日本人はバラエティーが大好き
昨今の「コスト削減」と「コンプライアンス強化」により、バラエティー作りにおいて、制約がますます多くなっているのは確かである。では、制約が増えれば面白い番組は作りにくくなるかと言えば、必ずしもそうとも限らないと思うのだ。
日本の笑いの芸能は、日中戦争から太平洋戦争を経て終戦に至るまでの問、公権力から厳しい制約を受け続けていた。昭和初頭にエノケン(榎本健二や古川ロイハといった大スターを輩出した浅草レヴューも、検閲制度などにより、コメディアンにとって最大の武器であるアドリブや時事謳刺、ナンセンスなドタバタ喜劇、レヴューに必要不可欠なアメリカ音楽の演奏などを次々に禁じられ、戦争協力劇の上演を強いられた。そんな状況下で、劇作家の菊田一夫が執筆した『ロッパ若し戦はば』(37年)と『ロッパと兵隊』(40年)は、戦争協力劇という枠を借りつつ、その時代の新しい喜劇のあり方を示した傑作であったと伝えられている。そこには菊田やロッパのプライドと意地があったのだろう。
BPOの意見書の「おわりに-バラエティーに新しい力と魅力を」では、「制作者としての内的必然性が伝わってくるバラエティーが見たい」と制作者へのエールが贈られると同時に、「ところが、いわば『当て逃げ』のような粗雑なネタ、『その場の軽いノリ』の悪ふざけを寄せ集めて作ったバラエティーがいささか目立つのではないだろうか」との現状への問題提起がなされている。
ここ数年のバラエティーは、多くの芸人を集めて彼らに何かテーマを与えてしゃべらせたり、芸をさせたりという形式のものが主流であり、この春の持番もゴールデンタイムから深夜枠まで、その種のものがとにかく多かった。中には『人志松本のすべらない話』(フジテレビ)や『アメトーーク』(テレビ朝日)といったバラエティー史に残る人気番組もあるが、これだけ同工異曲のものが続くと、さすがに他の形式のバラエティーの出現を期待したくなる。
全体的に、先に挙げたような往年のバラエティーの傑作と比べると、かなり小粒な印象のものが多いようにも感じる。
それを制約のせいにはしてもらいたくない。
3月11日に民放連の主催で行われたシンポジウム「バラエティー向上委員会」では在京民放5局の制作者が登壇し、「意見書を読んだか」との問いに48人が読んだと回答。「意見書をうっとうしいと思うか」という問いに対しては22人がそう思うと答えた。これを制約ととらえれば確かにうっとうしいのかもしれないが、ここは制作者へのエールと受け取って、真摯にバラエティーというものを見つめ直す一つの機会にしてもらいたいものだ。
地デジヘの完全移行を来年に控える。方で、全体的な視聴者のテレビ離れが懸念される今だからこそ、その必要があるのではないか。何だかんだ言っても、日本人の大半はバラエティー番組が大好きなのだから、その人たちに「バラエティー離れ」をさせないような番組作りを期待したい。 意見書の文体やたとえ話の表現に関しては好みも分かれるところだろうが、要所要所で言わんとしていることは基本的に問違っていないと思う。
「私たちは、バラエティー制作に精魂をこめる制作者たちが登場し、新しい力と魅力にあふれたバラエティーをたくさん見せてくれる日を待っている」–全くの同感である。
お笑い評論家・江戸川大学専任講師 西条昇